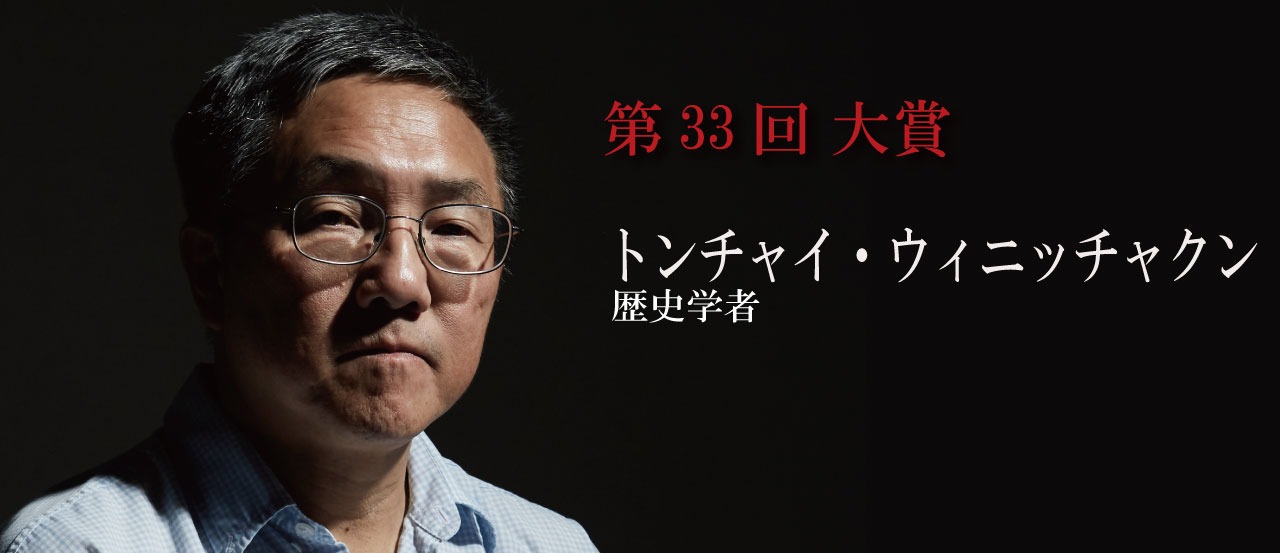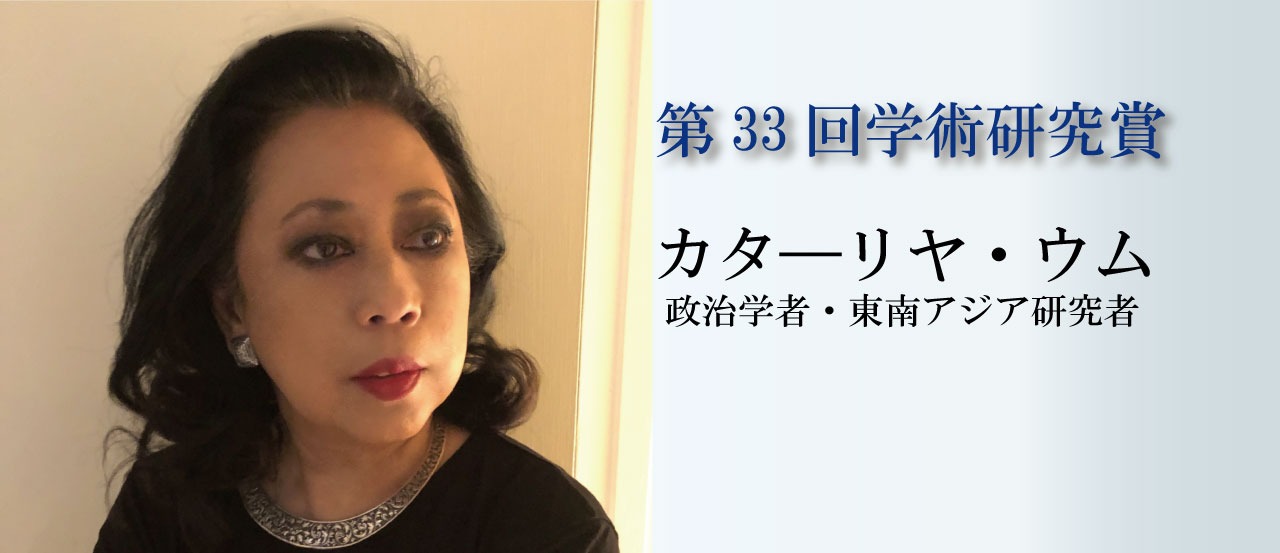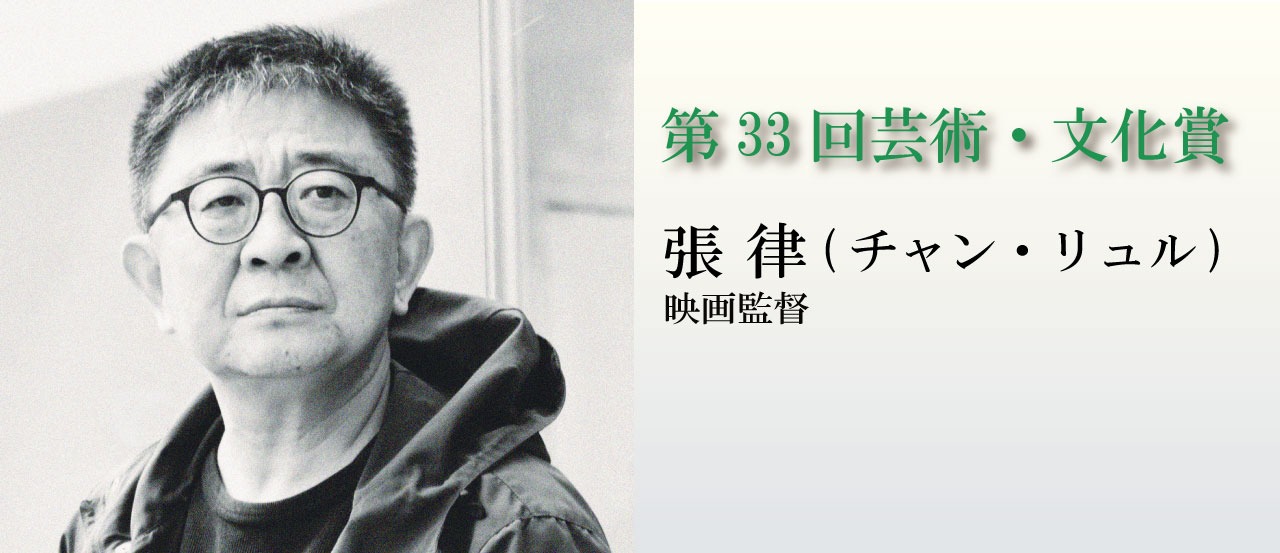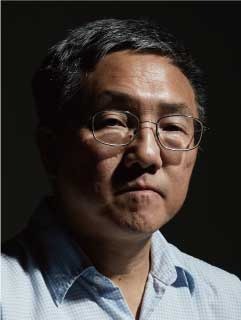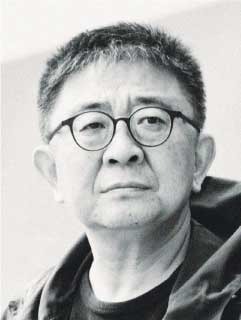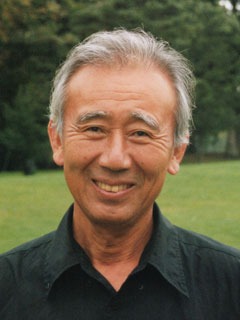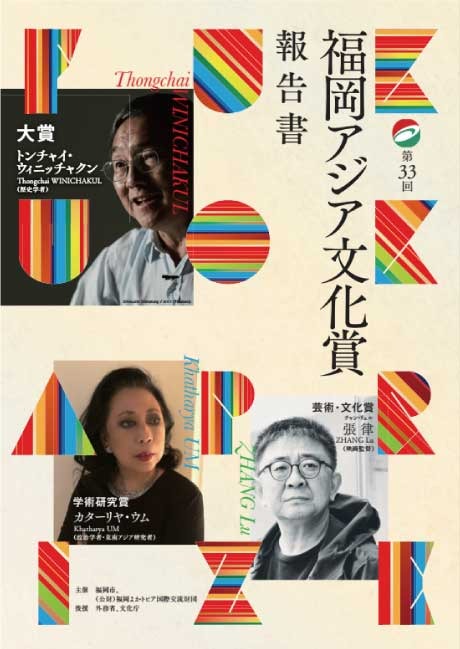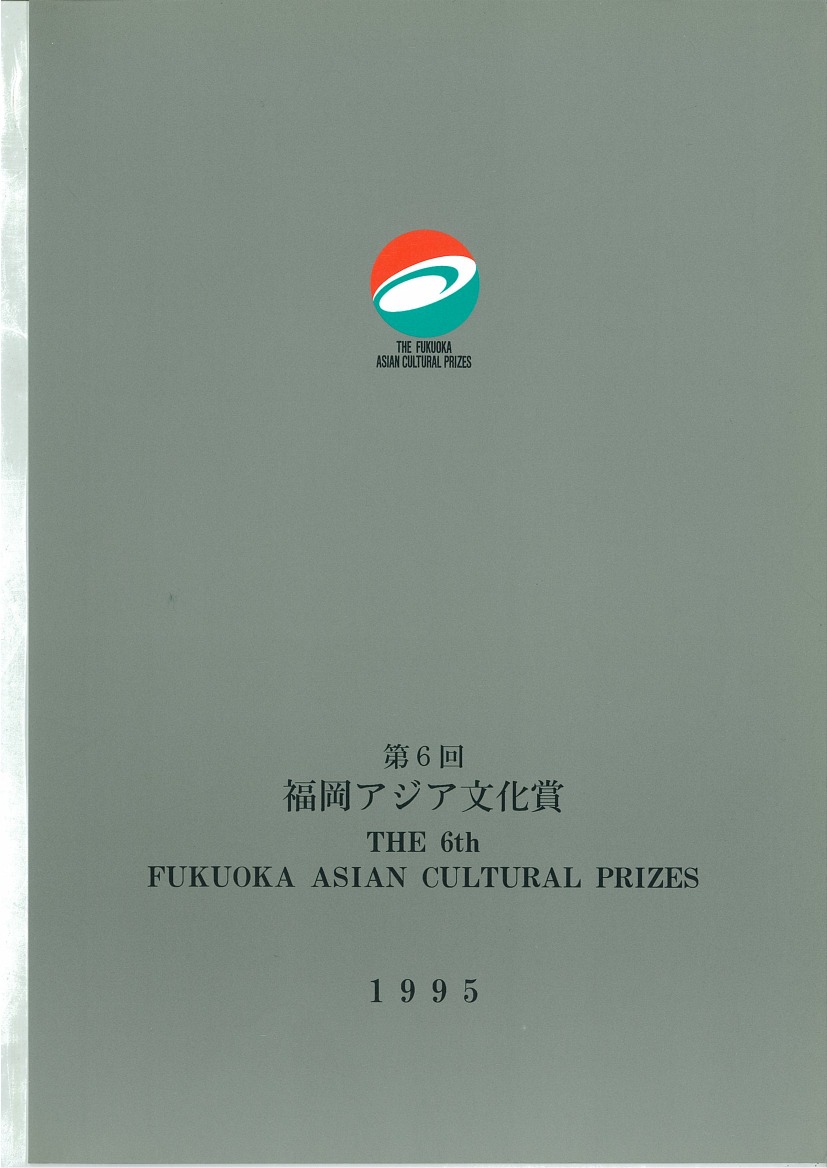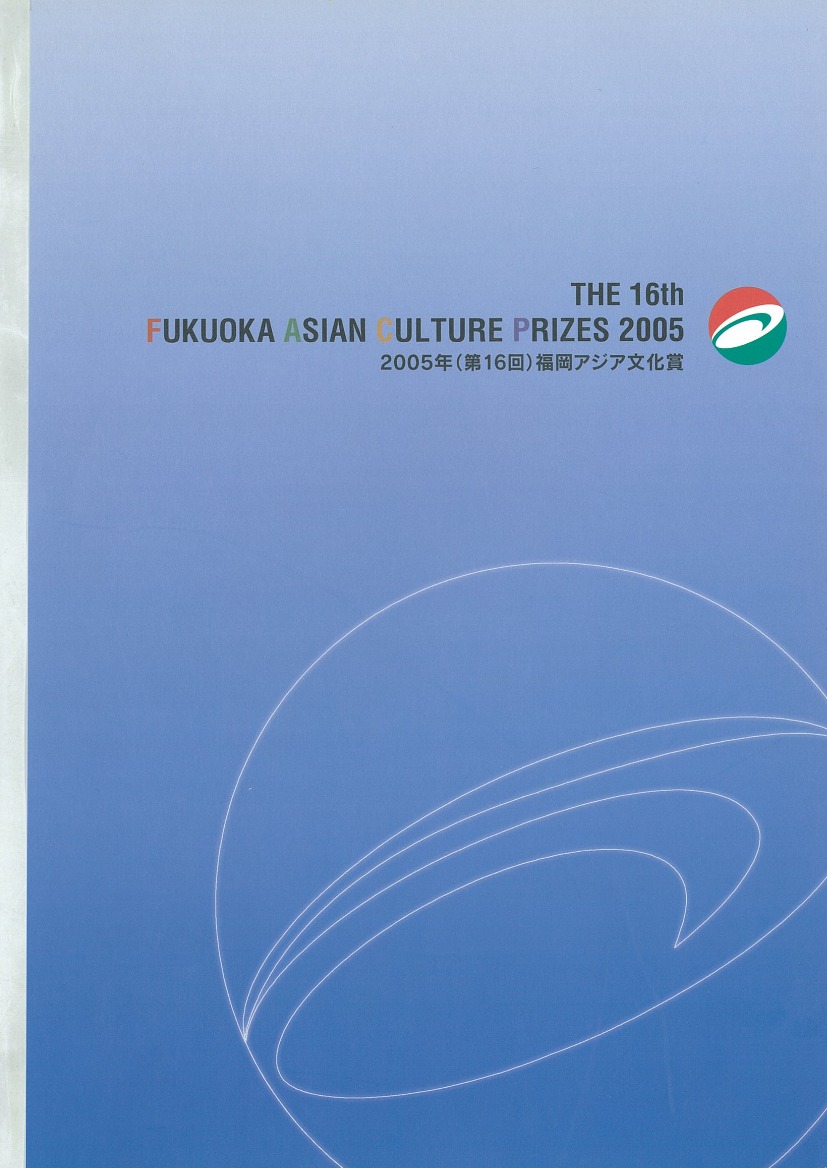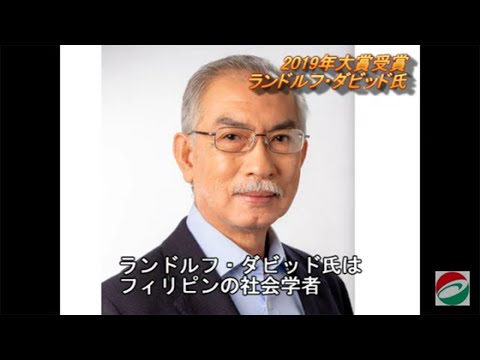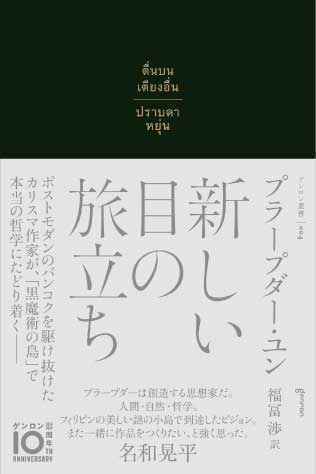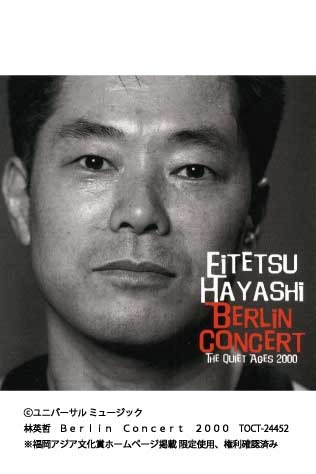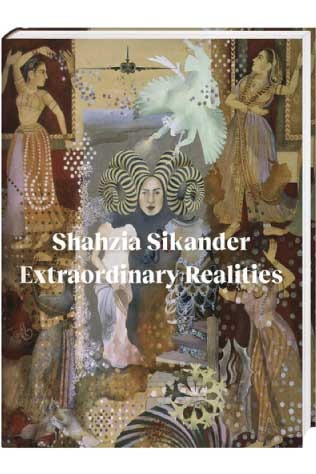LAUREATES OF THE FUKUOKA PRIZE
2023年(第33回)福岡アジア文化賞受賞者
FROM THE LIBRARY OF THE FUKUOKA PRIZE
これまでの福岡アジア文化賞
過去の記事をランダムに表示しています。Mail magazine
メールマガジン会員募集福岡アジア⽂化賞より、イベント情報・ニューストピックスなど、
いち早くお届けいたします。